― 知識は紙で、物語は電子で ―

💬 この記事のテーマ
Kindleも紙の本も、どっちも良いけど使い分けが難しい…。
そんな悩みに対して、私が実際に試してみてわかった“ちょうどいい使い分け方”を紹介します。
どっちで読むか、いつも迷っていた
本を読むのが好きな私は、Kindleも紙の本もどちらも使っています。
ただ、いつも迷っていました。
「やっぱり紙の方が頭に入るのかな?」
「でもKindleの手軽さは捨てがたい…」
どちらも良いところがあるのに、使い分けの基準が分からない。
その迷いがずっと続いていたんです。
目的を考えずに使っていたのが原因だった
あるときふと気づきました。
私が迷っていたのは、「読書の目的」を決めずに使っていたからでした。
Kindleも紙の本も「読む」という行為は同じですが、実は得意分野がまったく違うんです。
- Kindleは「手軽さ・持ち運び」に優れ、物語を流れるように読むのに向いている。
- 紙の本は「一覧性・記憶の定着」に優れ、知識を整理したり、調べたりするのに向いている。
これに気づくまでは、“なんとなく”で選んでいたので、どちらの良さも活かせていませんでした。
資格試験で感じた電子書籍の弱点
少し前、資格試験の勉強をしていたときに、参考書を電子書籍で購入したことがありました。
最初は「スマホで読めるし、職場の休憩中にも勉強できるから便利だな」と思っていたんです。
ところが実際に使ってみると、直接書き込みができない不便さに気づきました。
覚えたい箇所に線を引けず、ちょっとしたメモも書けない。
さらに、「あの解説もう一度読みたいな」と思っても、
ページを行き来するのがスムーズじゃなく、すぐに目的の場所に戻れないもどかしさがありました。
そのとき改めて、学び系の本は紙の方が圧倒的に使いやすいと感じたんです。
一方で紙の本にもデメリットはある
もちろん、紙の本にも不便な点があります。
- お風呂での読書には向かない。
- 寝る前の暗い照明だと読むことが出来ない。
- 増えすぎると保管場所に困る。
特に、寝る前ベッドでの読書が習慣の私にとっては、暗い照明の下では読むことができません。
「Kindleのバックライトって、本当にありがたいな」と実感する瞬間です。
ジャンルで使い分けてみた
そこで私は、読む内容によって使い分けることにしました。
📘 紙の本:知識・辞典・実用書など
紙の本は、ページをパラパラとめくったり、付箋を貼ったりできる。
辞典のように索引を調べる作業も直感的で、頭に残りやすいです。
書き込みやメモを残すと、自分の思考の跡が可視化されて、あとから見返すときにも役立ちます。
まさに「手で考える読書」といった感覚です。
📱 Kindle:小説・エッセイなどの物語系
一方で、Kindleは軽くてどこでも読めるのが魅力。
通勤時間やカフェの待ち時間、寝る前のベッドの中でも気軽に開けます。
ページをめくる動作が滑らかで、物語にすっと入り込める。
エッセイや小説のような“流れを味わう本”にはぴったりだと感じました。
実際にやってみて感じたこと
このスタイルを続けてみて、一番大きかったのは「読む目的がはっきりした」ことです。
以前は「どっちで読もうか」と悩んでいましたが、
今は本のジャンルによって自然に選べるようになりました。
- 学び系の本や参考書は紙の本で読むことで、
→ 重要な部分に線を引いたり、メモを書き込んだりできる。
→ ページを戻って確認するのもスムーズで、理解が深まる。 - 小説やエッセイなどの物語系はKindleで読むことで、
→ 場所を選ばず、気軽にストーリーの世界に浸れる。
→ 寝る前や外出先でも読書が続けやすい。
どちらも“使い分け”が正解
Kindleも紙の本も、どちらが上ということはありません。
それぞれに役割があり、使い分けこそが正解だと感じます。
- 調べながら学ぶ本 → 紙の本
- 物語を楽しむ本 → 電子書籍(Kindle)
このシンプルなルールを決めておくだけで、読書が驚くほど快適になります。
どちらかを我慢して使うより、両方をうまく活かす。
それが、長く読書を楽しむコツだと思います。
おわりに:自分だけの読書ルールを作ろう
読書は習慣だからこそ、自分に合ったスタイルを見つけることが大切です。
次に本を選ぶとき、「この本はどんな目的で読みたいか?」を少しだけ考えてみてください。
その答えが、自然と「Kindleか紙か」を教えてくれるはずです。
あなたの読書が、もっと心地よく、もっと自由になりますように。
📚 まとめ
| 読み方 | 向いている本 | 特徴 |
|---|---|---|
| 📘 紙の本 | 辞典・実用書・学び系 | 書き込み・メモがしやすい、記憶に残る |
| 📱 Kindle | 小説・エッセイ・物語系 | 軽くて手軽、どこでも読める |
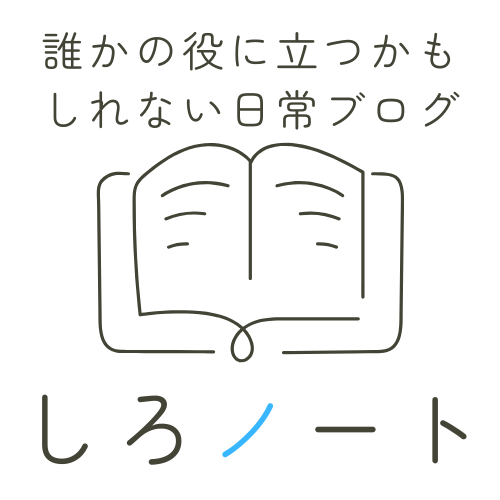
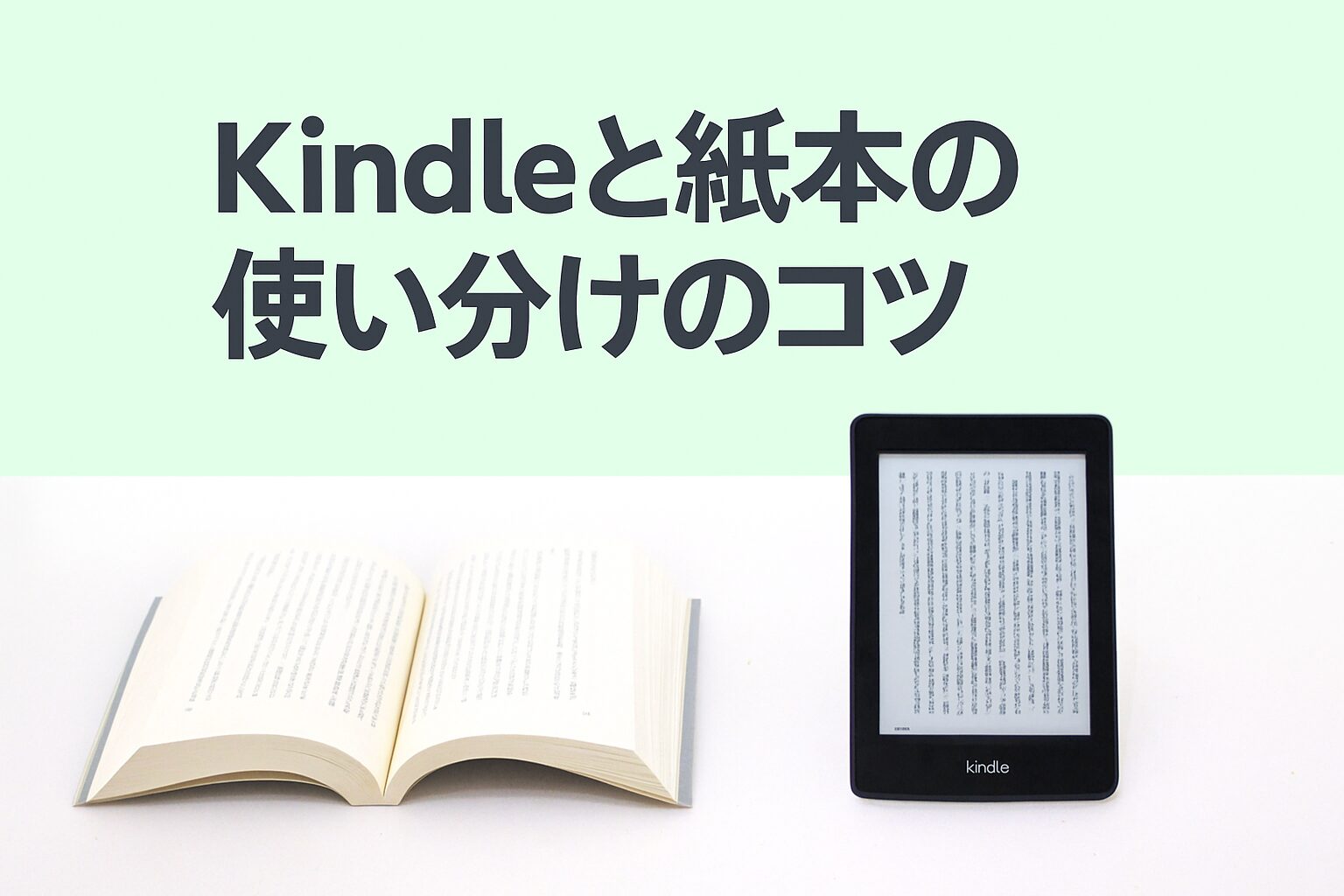


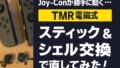
コメント